
静電容量式は、レベルスイッチ・レベル計ともに数多くの製品を擁する汎用性の高い検知・計測方式です。
このページでは、静電容量式の原理を具体的にご説明いたします。また、静電容量式には不可欠な用語である「誘電率」、および、様々な物質の「誘電率表」もご紹介します。是非そちらもあわせてご覧ください。
静電容量式レベルスイッチの概要
静電容量式レベルスイッチは、タンクやホッパー等の容器に取付穴を空け、電極部を挿入して使用します。測定物が電極に触れることにより、測定物の有無を検出してリレー出力します。電極の取付方向に水平、垂直、斜め等の限定はありません。

スイッチの測定原理について
静電容量式レベルスイッチでは、下記のような電極を使用します。

空の時の電気的な状態と、満の時の電気的な状態の違いを捉え、レベル検知を行います。空の時の検出電極と接地電極の電気的な状態は、抵抗値(Ro)が無限大で、静電容量(Co)は取付状態で決まる固定の静電容量値になります。
容器に測定物が入り電極付近が浸ると(満状態になると)、検出電極と接地電極間の抵抗値および静電容量値はRsまたはCsに変化します。この変化を捉えてレベル検知を行います。

この電気的変化は測定物によって異なります。
- 測定物が電気を通さない(絶縁性)場合は、抵抗はほぼ(∞)(Ω)で変化はほとんどありません。変化があるのは静電容量のみです。この静電容量の変化を捉えてレベル検知を行います。
- 測定物が電気を通す導電性の場合は、抵抗値が小さくなります。この抵抗の変化をとらえてレベル検知を行います。
- 測定物の中には、絶縁性でも導電性でもない、中間的な半導電性物質もあります。半導電性の物質は、抵抗の変化と静電容量の変化の両方が変化します。この変化をとらえてレベル検知します。
静電容量の原理について
金属性の板を平行にし電圧を加えると、静電容量を形成します。
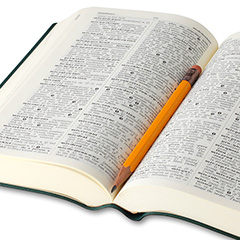
静電容量Cの値は、左図の式で算出できます。
Cは静電容量値、ε0は真空の誘電率で8.854×10-12、εsは絶縁体の誘電率です(εはイプシロンと読みます)。
金属板の間の静電容量値は、金属板の面積Sと金属板同士の距離L、および金属板の間の絶縁体の誘電率εsにより決定されます。絶縁体は固有の特性である比誘電率というものがあり、例えば空気は約1.0で、一般的な絶縁性の粉体の場合2.0~5.0程度です。SとLが同じ場合は、静電容量Cは絶縁体の誘電率により変化します。つまり、静電容量式レベルスイッチは静電容量値Cの変化を捉えることで、物質の検知・計測を行っているのです。レベルスイッチの接地電極と検出電極それぞれの金属板と同じ働きをします。金属板の間の絶縁体がレベル検知を行う測定物質になります。
今、仮に空気の場合(空の状態)の静電容量が2PFとした場合に、誘電率が3.0の粉体が電極間に入った場合、静電容量は6PFになります。よって、静電容量の差は4PFになります。
静電容量式レベルスイッチはこの原理(静電容量の変化を感知)を応用しています。
- 電極形状によって変化する静電容量
-
金属性の板(導電体)の間に介在する物質の性質によっても静電容量は変わりますが、金属板の面積や金属板間の距離を変える事によっても静電容量は変わります。
金属板の面積を1/2にすれば静電容量も1/2になり面積を2倍にすれば静電容量も2倍になります。従って、静電容量が導体問の関係によって決定されることから、簡単な形状については静電容量を求める式が公式化されています。
下記に4種類の電極における静電容量Cを求める式を記載します。
![]()
ただし、一般的にはこのように理想的な形状ではないため、数式で静電容量を導き出すことは困難です。そのために用いられるのが、静電容量測定器です。弊社の静電容量測定器は、長年培ってきた知識やノウハウが凝縮された製品ですので、正確な静電容量値計測をご希望の方はぜひご検討ください。
静電容量の数学的説明について
静電容量式レベルスイッチ測定原理を数式的に説明します。
今、仮に直径100mmの金属容器に(Φ)10×40mmの検出電極を挿入した場合を考えてみます。
容器は、※2の図の接地部(アース、接地電極)になります。
-
容器の中が空の場合、静電容量は次式で求めることができます。
![]()
-
次に絶縁性の液を容器に入れると、静電容量は次式で求めることができます。
![]()
つまり、容器が空の場合の静電容量値と、液が入った場合の静電容量値との差が変化容量となり、レベル検出をします。
ΔC =C1-C0 =1.93-0.96 =0.97PF になります。
上記の変化容量(ΔC=0.97PF)により、液体の検知を行うことができます。
静電容量式の付加機能について
弊社の静電容量式レベルスイッチは上記の基本原理に加えて、多様な測定物への計測や、さまざまな状況に対応できる応用技術を有しています。付着補正機能(測定物が電極に付着した場合に付着をキャンセルする機能)や導電性、半導電性などの各測定物に対応したアンプ機能など、お客様の測定物や測定条件に合わせてご提案いたします。また、測定物の強度や性質などに合わせた豊富な電極のラインアップもご用意しております。
各物質の誘電率「誘電率表」
前述した各物質の誘電率をまとめた誘電率表をご紹介します。
静電容量式のレベルスイッチ・レベル計は、こうした固定の誘電率を元に検知・計測しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。
- パウダーなどの誘電率には注意が必要!?
- 実は下記の誘電率の値は、それぞれの物質の通常の形状時とお考えください。パウダー状やフレーク状になった測定物は、物質中に空気(誘電率が、1.000586)が混入されるため、通常の形状時よりもはるかに誘電率が低くなります。また、温度変化によっても誘電率は変化することがあります。あくまでも誘電率は目安とお考えください。
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
- ら行
| アクリル樹脂 | 2.7~4.5 |
|---|---|
| 雲母 | 4.5~7.5 |
| アクリルニトリル樹脂 | 3.5~4.5 |
| AS樹脂 | 2.6~3.1 |
| アスファルト | 2.7 |
| ABS樹脂 | 2.4~4.1 |
| アスベスト | 3~3.6 |
| エタノール | 24 |
| アセチルセルローズ | 2.5~7.5 |
| エチルエーテル | 4.3 |
| アセテート | 3.2~7.0 |
| エチルセルローズ | 2.8~3.9 |
| アセトン | 19.5 |
| エチレングリコール | 38.7 |
| アニリン | 6.9 |
| エチレン樹脂 | 2.2~2.3 |
| アニリン樹脂 | 3.4~3.8 |
| エポキシ樹脂 | 2.5~6 |
| アニリンホルムアルデヒド樹脂 | 4 |
| エボナイト | 2.5~2.9 |
| アマニ油 | 3.2~3.5 |
| 塩化エチレン | 4.0~5.0 |
| アミノアルキル樹脂 | 3.9~4.2 |
| 塩化銀 | 11.2 |
| アランダム | 3.2~3.4 |
| 塩化ナトリウム | 5.9 |
| アルキッド樹脂 | 5 |
| 塩化パラフィン | 2.27 |
| アルコール | 16~31 |
| 塩化ビスマス | 2.75 |
| アルミナ磁器 | 8.0~11 |
| 塩化ビニール樹脂 | 2.8~8.0 |
| アルミナ被膜 | 6~10 |
| 塩化ビニリデン樹脂 | 3.0~5.0 |
| アルミノアルキド樹脂 | 3.9 |
| 塩素(液) | 2 |
| アルミン酸ソーダ | 5.2 |
| 塩素化ポリエーテル樹脂 | 2.9 |
| アンモニア | 15~25 |
| 塩ビ(粉末) | 3.2~4 |
| イソオクタン | 3.0~3.5 |
| エンビキューブ(赤) | 2.15~2.24 |
| イソフタル酸 | 2.2 |
| 塩ビ樹脂 | 5.8~6.4 |
| イソブチルアルコール | 17.7~18.0 |
| 塩ビ粒体 | 1.5~4.0 |
| イソブチルメチルケトン | 13.0~14.0 |
| 石綿 | 1.4~1.5 |
| 鋳物砂 | 3.384~3.467 |
| 硫黄 | 3.4 |
| ウレタン | 6.5~7.1 |
| カーバイト粉 | 5.8~7.0 |
|---|---|
| クロロナフタリン | 3.5~5.4 |
| カゼイン樹脂 | 6.1~6.8 |
| クロロピレン | 6.0~9.0 |
| ガソリン | 2.0~2.2 |
| クロロホルム | 4.8 |
| 紙 | 2.0~2.5 |
| ケイ酸カルシウム | 2.4~5.4 |
| 紙・フェノール積層板 | 5.0~7.0 |
| ケイ砂 | 2.5~3.5 |
| ガラス | 3.7~10.0 |
| ケイ素 | 3.5~5.0 |
| ガラス・エポキシ積層板 | 4.5~5.2 |
| 軽油 | 1.8 |
| ガラス・シリコン積層板 | 3.5~4.5 |
| 原油(KW#9020.01%) | 2.428強 |
| ガラス飲料 | 2.0~2.5 |
| 硬質塩ビ樹脂 | 2.8~3.1 |
| ガラスビーズ | 3.1 |
| 硬質ビニルブチラール樹脂 | 3.33 |
| ガラスポリエステル積層板 | 4.2~5 |
| 鉱油 | 2~2.5 |
| 顆粒ゼラチン | 2.615~2.664 |
| 氷 | 4.2 |
| 過リン酸石 | 14.0~15.0 |
| コーヒー粕 | 2.4~2.6 |
| カルシウム | 3 |
| コールタール | 2.0~3.0 |
| ギ酸 | 58.5 |
| 黒鉛 | 12.0~13.0 |
| キシレン | 2.3 |
| 穀類 | 3.0~5.0 |
| キシロール | 2.7~2.8 |
| ココア粕 | 2.5~3.5 |
| 絹 | 1.3~2 |
| 骨炭 | 5.0~6.0 |
| 金剛石 | 16.5 |
| こはく | 2.8~2.9 |
| 空気 | 1.000586 |
| ごま(粒状) | 1.8~2.0 |
| 空気(液体) | 1.5 |
| ゴム(加硫) | 2.0~3.5 |
| グラニュー糖(粉末) | 1.5~2.2 |
| ゴム(生) | 2.1~2.7 |
| グリコール | 35.0~40.0 |
| 小麦 | 3.0~5.0 |
| グリセリン | 47 |
| 小麦粉 | 2.5~3.0 |
| クレー(粉末) | 1.8~2.8 |
| ゴムのり | 2.7~2.9 |
| クレゾール | 11.8 |
| 米の粉 | 3.5~3.7 |
| クローム鉱石 | 8.0~10.0 |
| コンパウンド | 3.6 |
| クロマイト | 4.0~4.2 |
| 蛍石 | 6.8 |
| 顆粒ゼラチン | 2.615~2.664 |
| 酢酸セルローズ | 3.2~7 |
|---|---|
| シンナー | 3.7 |
| 砂糖 | 3 |
| 酢 | 37.6 |
| さらしこ | 1.8~2.0 |
| 水酸化アルミ | 2.2 |
| 酸化亜鉛 | 1.7~2.5 |
| 水晶 | 4.6 |
| 酸化アルミナ | 2.14 |
| 水晶(熔融) | 3.5~3.6 |
| 酸化エチレン | 4.0~5.0 |
| 水素 | 1.000264 |
| 酸化第二鉄(粉末) | 1.4~1.8 |
| 水素(液体) | 1.2 |
| 酸化チタン | 83~183 |
| 水溶液 | 50~80 |
| 酸化チタン磁器 | 30~80 |
| 酢酸 | 6.2 |
| 酸素 | 1.000547 |
| 酢酸エチル | 6.4 |
| ジアレルフタレート | 3.8~4.2 |
| 酢酸セルローズ | 3.2~7.0 |
| ジアレルフタレート樹脂 | 3.3~6.0 |
| 酢酸ビニル樹脂 | 2.7~6.1 |
| シェビールベンゼン | 2.3 |
| スチレン樹脂 | 2.3~3.4 |
| シェラック | 2.3~3.8 |
| スチレンブタジェンゴム | 3.0~7.0 |
| シェラックワニス | 2.8~4.7 |
| スチロール樹脂 | 2.4~2.8 |
| シェル砂 | 1.2 |
| ステアタイト | 5.3~6.8 |
| 四塩化炭素 | 2.2~2.6 |
| ステアタイト磁器 | 6~7 |
| 塩 | 3.0~15.0 |
| 砂 | 3.0~5.0 |
| 磁器 | 4.0~7.0 |
| スレート | 6.6~7.4 |
| シケラック | 2.3~3.8 |
| 石英(溶解) | 3.5~4.5 |
| シケラックワニス | 2.8~4.7 |
| 石英 | 3.7~4.1 |
| 砂利 | 5.4~6.6 |
| 石英ガラス | 3.5~4.0 |
| 重クロム酸ソーダ | 2.9 |
| 石炭酸 | 10 |
| 充填用コンパウンド | 3.6 |
| 石綿 | 3~3.5 |
| 硝酸鉛 | 37.7 |
| 石油 | 2.0~2.2 |
| 硝酸バリウム | 5.9 |
| 石膏 | 5.3 |
| 硝石灰(粉末) | 1.8~3.0 |
| セビン | 1.6~2.0 |
| シリカアルミナ | 2 |
| セルロイド | 4.1~4.3 |
| シリコン | 2.4 |
| セルローズ | 6.7~8.0 |
| シリコンゴム | 3.0~3.5 |
| セレニューム | 6.1~7.4 |
| シリコン樹脂 | 3.5~5 |
| セレン | 6.1~7.4 |
| シリコン樹脂(液) | 3.5~5.0 |
| セロファン | 6.1~7.7 |
| シリコンワニス | 2.8~3.3 |
| 象牙 | 1.9 |
| 飼料 | 3.0~5.0 |
| ソーダ石灰ガラス | 6.0~8.0 |
| 真空 | 1 |
| 大豆油 | 2.9~3.5 |
|---|---|
| デキストリン | 2.2~2.4 |
| 大豆粕 | 2.7~2.8 |
| テフロン(4F) | 2 |
| ダイヤモンド | 16.5 |
| テレクル酸 | 1.5~1.7 |
| 大理石 | 3.5~9.3 |
| テレフタル酸 | 約1.5~1.7 |
| たばこ(きざみ) | 1.5 |
| 天然ゴム | 2.7~4.0 |
| タルク | 1.6~2.0 |
| 陶磁器 | 4.4~7.0 |
| ダルサム | 3.2 |
| 陶器類 | 5~7 |
| 炭酸ガス | 1.000985 |
| とうもろこし粕 | 2.3~2.6 |
| 炭酸ガス(液体) | 1.6 |
| 灯油 | 1.8 |
| 炭酸カルシウム | 1.58 |
| トクシール | 1.45 |
| 炭酸ソーダ | 2.7 |
| トランス油 | 2.2~2.4 |
| チオコール | 7.5 |
| トリクレン | 3.4 |
| チタン酸バリウム | 1200 |
| トルエン | 2.3 |
| 窒素 | 1.000606 |
| ドロマイド | 3.1 |
| 窒素(液体) | 1.4 |
| 粒状ガラス(0010) | 6.32 |
| 長石質磁器 | 5~7 |
| 粒状ガラス(0080) | 6.75 |
| 鋳砂物 | 3.384~3.467 |
| ナイロン | 3.5~5.0 |
|---|---|
| ニトロベンゼン | 36 |
| ナイロン-6 | 3.5~4.0 |
| 尿素 | 5~8 |
| ナイロン-6-6 | 3.4~3.5 |
| 尿素樹脂 | 5.0~10.0 |
| ナフサ | 1.8 |
| 尿素ホルムアルデヒド樹脂 | 6.0~9.0 |
| ナフタリン | 2.5 |
| 二硫化炭素(液) | 2.6 |
| 軟質塩ビ樹脂 | 3.3~4.5 |
| ネオプレン | 6~9 |
| 軟質ビニルブチラール樹脂 | 3.92 |
| ネスカフェ粉 | 0.55~0.7振動 |
| 二酸化酸素(液) | 2.6 |
| のり(粉末) | 1.7~1.8 |
| 二酸化チタン | 100 |
| ノルマルヘキサン | 2 |
| 二酸化マンガン | 5.1 |
| ノルマルヘプタン | 1.92 |
| ニトロセルローズラッカー | 6.7~7.3 |
| PEキューブ | 1.55~1.57 |
|---|---|
| プロピオネート | 3.3~3.8 |
| PVA-E(オガクズ状) | 2.23~2.30 |
| プロピレングリコール | 32 |
| Pビニールアルコール | 1.8 |
| 粉末アルミ | 1.6~ |
| バーム粕 | 3.1 |
| ペイント | 7.5 |
| バイコール | 3.8 |
| ベークライト | 4.5~5.5 |
| パイレックス | 4.8 |
| ベークライトワニス | 3.5~4.5 |
| 白雲母 | 4.5~7.5 |
| ヘリウム(液体) | 1.05 |
| 蜂蜜 | 2.9 |
| ベンガラ | 2.6 |
| 蜂蜜蝋 | 2.9 |
| ベンジン | 2.3 |
| パナジウムダスト | 2.6 |
| ベンジンアルコール | 13.1 |
| パラフィン | 1.9~2.5 |
| 変成器油 | 2.2 |
| パラフィン油 | 4.6~4.8 |
| ベンゼン | 2.3 |
| パラフィン蝋 | 2.1~2.5 |
| 方解石 | 8.3 |
| ビニールアルコール | 1.8~2.0 |
| 硼珪酸ガラス | 4.0~5.0 |
| ビニルホルマール樹脂 | 3.0~3.7 |
| 蛍石 | 6.8 |
| ピラノール | 4.4 |
| ポリアセタール樹脂 | 3.6~3.7 |
| ファイバー | 2.5~5 |
| ポリアミド | 2.5~2.6 |
| フィルム状フレーク(黒) | 1.17~1.19 |
| ポリウレタン | 5.0~5.3 |
| フェノール(石灰酸) | 9.78 |
| ポリエステル樹脂 | 2.8~8.1 |
| フェノール紙積層板 | 4.6~5.5 |
| ポリエステルペレット | 3.2 |
| フェノール樹脂 | 3.0~12.0 |
| ポリエチレン | 2.3~2.4 |
| フェノールペレット | 2.0~2.6 |
| ポリエチレン(高圧) | 2.2 |
| フェラスト(粉末) | 1.4~ |
| ポリエチレン(低圧) | 2.3 |
| フェロークローム | 1.5~1.8 |
| ポリエチレンオキサイト | 7.8 |
| フェロシリコン | 1.38 |
| ポリエチレン架橋 | 2.3~2.4 |
| フェロマンガン | 2.8~3.2 |
| ポリエチレンテレフタレート | 2.9~3 |
| フォルステライト磁器 | 5.8~6.7 |
| ポリエチレンペレット | 1.7 |
| ブタン | 20 |
| ポリカーポネート | 2.9~3 |
| ブチルゴム | 2.5~3.5 |
| ポリカーポネート樹脂 | 2.9~3.0 |
| ブチレート | 3.2~6.2 |
| ポリカ粉 | 1.58 |
| フッ化アルミ | 2.2 |
| ポリスチレン | 2.4~2.6 |
| フッ素樹脂 | 4.0~8.0 |
| ポリスチレンペレット | 1.5 |
| ぶどう糖 | 3.0~4.0 |
| ポリスチロール | 2.0~2.6 |
| 不飽和ポリエステル樹脂 | 2.8~5.2 |
| ポリスルホル酸 | 2.8 |
| フライアッシュ | 1.5~1.7 |
| ポリビニールアルコール | 2 |
| フラックス | 3 |
| ポリブチレン | 2.2~2.3 |
| フラン樹脂 | 4.5~10.0 |
| ポリブチレン樹脂 | 2.25 |
| フルフラル樹脂 | 4.0~8.0 |
| ポリプロピレン | 2.0~2.3 |
| フレオン | 2.2 |
| ポリプロピレン樹脂 | 2.2~2.6 |
| フレオン11 | 2.2 |
| ポリプロピレンペレット | 1.5~1.8 |
| フレキシガラス | 3.45 |
| ポリメチルアクリレート | 4 |
| プレスボード | 2.0~5.0 |
| ホルマリン | 23 |
| プロバン(液体) | 1.6~1.9 |
| フイルム状フレーク(黒) | 1.17~1.19 |
| マーガリン液 | 2.8~3.2 |
|---|---|
| メタクリル樹脂 | 2.2~3.2 |
| マイカ | 5.7~7.0 |
| メタノール | 33 |
| マイカナイト | 3.4~8.0 |
| メチルバイオレット | 4.6 |
| マイカレックス | 6.5~9.5 |
| メラミン樹脂 | 4.7~10.2 |
| 松根油 | 2.5 |
| メラミンホルムアルデヒド樹脂 | 7.0~9.0 |
| 松脂(粉末) | 1.65 |
| メリケン粉末 | 3.0~4.5 |
| ミクロヘキサン | 2 |
| 綿花種油 | 3.1 |
| 水 | 80 |
| 木綿 | 3~7.5 |
| 蜜ろう | 2.5~2.9 |
| 木材(水分による) | 2.0~6.0 |
| 雪 | 3.3 |
|---|---|
| 4フッ化エチレン樹脂 | 2 |
| ユリア樹脂 | 3.4~6.9 |
| 硫化バナジウム | 3.1 |
|---|---|
| リン鉱石 | 4 |
| 硫酸マグネシューム(粉) | 2.7強 |
| リン酸カルシウム | 1.9~3.2 |
| 粒状ガラス(0010) | 6.32 |
| ルビー(光軸に直角) | 13.27 |
| 粒状ガラス(0080) | 6.75 |
| ルビー(光軸に平行) | 11.28 |
| 緑柱石(光軸に直角) | 7.02 |
| ロッシェル塩 | 100~2000 |
| 緑柱石(光軸に平行) | 6.08 |
| ワセリン | 2.2~2.9 |
|---|---|
PAGE NAVIGATION
会員登録(無料)をして頂くと、製品のカタログ、取扱説明書、図面等がダウンロードできます。
各種カタログがダウンロード可能です
会員登録(無料)をして頂くと、製品のカタログ、取扱説明書、図面等がダウンロードできます。









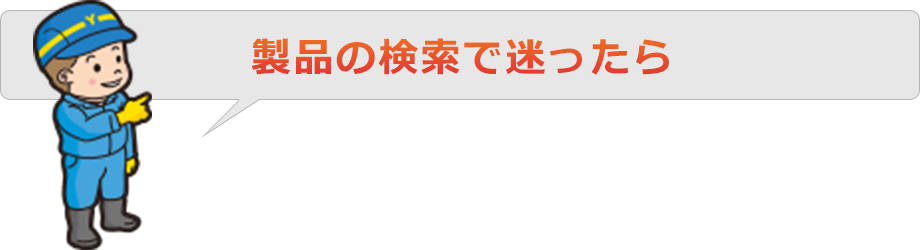



静電容量って?
静電容量とは、「電気エネルギーの貯蔵容量」といえるものです。
静電容量は、絶縁された導体間(離されて配置された2つの導電体間)において、どの程度の電荷が蓄えられるかを表す量を意味します。英語ではキャパシタンス(capacitance)と呼ばれています。水に例えますと、ある水位(電圧V)においてどれだけの水量(電荷Q)を蓄えられるかという貯蔵量を表すものです。
前述しました様に、空間に配置された二つの導電体の間には必ずこの静電容量が作られます。その静電容量の値は、二つの導電体の距離と形状、導電体の間の空間の性質によって決定されます。
静電容量の記号はC(キャパシタンスのCです)、単位はファラッド(F)を使用します。但し、実際には、
という単位が用いられます。当社の製品カタログに記載されている静電容量の値の単位もpFです。
空気の誘電率(1.0)が水の誘電率(80)に変化すれば、静電容量Cが変化し、水が貯蔵された事が判明する訳です。それでは、各物質が持っている「誘電率」とはどのようなものでしょうか?
静電容量式のレベル検出に必要な誘電率の簡単な説明を以下に行います。
誘電率って?
誘電率(比誘電率)とは、気体、液体、固体を問わず、絶縁性物質の持つ基本的な電気的定数です。各物質は固有の誘電率を持っており、誘電率の値は外部から電場を与えたとき各物質の中に存在している電子がどのように応答するかによって決まっています。
また、誘電率は絶縁性物質の定数なのですが、導電性のある物質が対象外という訳では有りません。半導体は誘電率を持ちますし、一見導電性と思われる物質の中にも誘電率を有することがあります。
導体と絶縁体の電気的作用の違いは、自由電子(金属内を自由に移動できる電子)の存在の違いによるものです。絶縁体には自由電子が存在しない為に電気を流すことができませんが、この絶縁体を電界内に置くと、電子分極という現象が発生し、この分極の強弱が比誘電率の差となります。この現象が結果として静電容量の変化となって現れます。
少し難しい話が続きましたが、真空では誘電率は1.0(空気の場合は約1.0)、水の場合は約80の誘電率を有しています。
導電性物質は誘電率が大きく、絶縁性物質は誘電率が小さくなります。
一部の物質は状態(粉体~塊体など)や環境によって誘電率が変化することがあります。
下記に記載されています様に様々な物質(測定物)がそれぞれ固有の誘電率を持っています。
比誘電率とは、誘電率εと真空の誘電率ε0の比(ε/ε0)を意味しています。
どのような絶縁性物質も必ず真空より大きな誘電率を有しているため、静電容量測定を通じた誘電率の測定により、様々な物質(測定物)の有無や量は勿論、成分、混合比、濃度等を計測できる訳です。
静電容量と誘電率を活用することにより、様々な物質のレベル検知やレベル計測が可能になります。